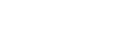能登半島地震視察2(ブログ3976)
- 2025年04月01日
今日は、9時に石川県庁を訪ねました。
今回は、全国組織の「広範な国民連合」で知り合った石川県議会・盛本芳久議員がセッテイングしてくれ、災害復旧担当課長他から、レクチャーを受けました。
地震は24年1月1日午後4時10分に発生、石川県内は、震度7の志賀町、輪島市、そして全ての構成自治体が震度5以上の地震に見舞われ、2分後に津波警報、12分後に大津波警報が出されました。
今回の能登半島地震は、三方を海に囲まれ、平地が少ない半島という地理的な制約に加え、拠点都市から離れた過疎・高齢化の割合が極めて高い社会的な制約が有る地域で発生、死者549人(うち災害関連死321人)、負傷者1,267人(うち重症391人)、避難者約34,000人、住家被害115,681棟となり、石川県の災害非難計画でもまったく想定していない、それを大きく超える地震、そして石川県の地勢からか、多くの山間部での地滑りと海岸線隆起というこれまでの経験則では計り知れない自然災害だったとのことでした。地震による建物崩壊、特に民家では1階が潰れて2階が下に落ちてくる被害が多かったようで、建物が総じて古いことから、1階が揺れに耐えられなかったという特徴が有りました。
避難所は、インフラが寸断されていたことから、物資がなかなか思い通りにならず、当初は自衛隊員が背負って運ぶのが主となり、ヘリは避難を中心に活動、支援は早かったが被災地に届かなく、平時の想定と有事の実態は大きなギャップがあったとのことで、その場対応も多かったと話していました。
先ほど記載した様な地勢から、救援は困難な中での遂行となってしまい、県民には少なからず不安を与えてしまったのではないかというのが感想です。
1次避難から2次避難はコミュニティー維持を重視し、自衛隊や受け入れ市町の協力も得ながら集落“まるごと避難”を実施、その後、仮設住宅も用意しましたが、ここでもコミュニティーを重視した対応を行っていました。
今回の地震で、通信復旧はとても重要なことと、自立型のインフラは今後の課題ですが、非常に大事である事、また、実働部隊との意思疎通と連携は日常的に重視することは必至だという事が改めて知らされたということでも有ったようです。
1次産業、農業は復旧するまで94%が政府の補償で、土壌の変化流木の取り除きなどは、復旧は約500haのうち150haほど、水産業は被害のない漁港に移ってもらって操業、カニ漁には間に合わせる事を重視。
様々な事を質問をしましたが、救援、復旧に対してまだまだ検証が必要で、本音で話す所までには少し時間がかかるような気がしました。
それだけ、関わっている県職員やそれぞれの市町職員の忸怩たる重いが伝わってきました。