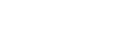再エネ賦課金(ブログ3874)
- 2025年03月25日
今月14日、衆院環境委員会で日本保守党の竹上祐子氏が「再エネ賦課金」について質問、「平成24年度の制度開始から今年度までの国民負担の累計は約23兆円にのぼる。
23兆円は子ども家庭庁の来年度一般会計予算案約4兆2千億円の5倍以上に相当する。賦課金は来年度の国民負担として約3兆円が見込まれ、累計額は約26兆円になる。
「年々増加する賦課金は実質的なステルス増税だ」として即時廃止を求めました。
これに対し経産省は、「エネルギーの安定供給と脱炭素を両立する観点から、再エネの導入を進める事が必要だ。」、そして「国民負担の抑制も重要な課題で、FIT、FIP両制度で買い取り価格の引き下げや入札制の活用によるコスト低減も進んでいる。引き続き政府全体で地域との共生と国民負担の抑制を前提に進めていきたい。」と話し、再エネ賦課金の廃止を否定しました。
その言葉とは裏腹に経産省は、再エネ賦課金の令和7年度分単価について1kwあたり3.98円に設定したと発表しました。これは、今年度の3.49円に比して0.49円の引き上げとなり、標準家庭(使用量400kwh)で電気料金に月額1,592円、年額1万9,104円が上乗せされます。国民全体の負担見込みは、6年度より約3,784億円増加となり、先ほどの質問にもありましたが国民が負担する再エネ賦課金は総額3兆634億円で、初めて3兆円を超えることになります。適用は5月検針分からで、引き上げ額は平均世帯月額196円、年額2,352円となります。
脱炭素、再エネの普及については否定するわけもありませんが、いつも原発推進派からは「再エネは賦課金が徴収される。再エネが増えれば増えるほど国民負担が大きくなる。だから原発の再稼働や新設は必要。」という口実を与える事になります。
今後、道内では洋上風力発電の事業化が加速することになりますが、それは、再エネ賦課金が今後も私たちに重くのしかかってくるということに他なりません。
エネルギー問題は政府の責任で行うものであり、国民の負担ありきが前提となれば、逆の立場で再エネの推進に反対する国民も出てくる事が懸念されます。
青森県では、太陽光・風力発電施設に自治体独自で課税する条例が可決しました。
この条例は、使い道を特定しない法定外普通税とし、総務相の同意を得て7年度中の導入を目指しています。
課税対象は2千kw以上の太陽光発電施設、500kw以上の陸上風力発電施設となっています。この課税は財政の厳しい自治体の収入増としては有り得る事ですが、これによって住民税が引き下げられる事は無いと思います。一方では事業者の税負担が増加する事からが計画を控えてしまう事も多少懸念されます。
先ほど経産省は「国民負担の抑制も重要な課題」と言っていましたが、再エネ事業者は賦課金で経営が安定し、自治体は再エネ事業者に課税をして財源を確保出来ますが、住民は今後も再エネ賦課金による負担が続きます。
つまり、エネルギー問題で犠牲になるのは常に住民ということでは無いかという疑問が膨らみ、憤りさえ覚えます。
※明日から、能登地震被災地に視察に行くことからブログは今週お休み致します。