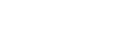国民の鬱積の行方(ブログ3896)
- 2025年04月21日
通常国会も折り返しとなり、夏の参議院選挙に向けて物価高騰の影響やトランプ関税の影響に対する国民生活への補填策として、政府から国民一人当たり3万円~5万円の給付について検討しようという案が出されましたが、自民党から選挙前のバラマキと思われることを危惧して、政府もこの案を撤回しました。
その間隙を突いて野党から、消費税減税の検討が各党から出されています。
一定の期間食料品だけ消費税をゼロにする、全ての消費税を5%減税する等々、野党各党は、自分達の案に賛成して貰おうと、多数化工作を繰り広げています。
一方、市内を歩くと「あの話し(給付金)は無くなったのか」と良く聴かれます。
「米の値段も一向に下がらず、生活が大変だ」という率直な声だと思いますが、「給付金は政府が皆さんに支給するのでは無く、皆さんの税金から給付する事になるので、その原資は、いずれかの形で皆さんか或いは将来の方々が負担することになるのでは無いでしょうか」と話すと、「それもそうだな」と返ってきます。
しかし、現実の問題としてこれだけ物価が高騰し、所得はそれに見合っていないことは明らかであり、政府が何らかの対策を打たなければ、国民のフラストレーションは溜まるばかりとなってきます。
さて、安倍政権が行ってきた「アベノミクス」は「大企業や富裕層が潤えば、そのしずくが滴り落ちてくる」と期待感を持たせましたが、全くの幻想でしか有りませんでした。
今の日本社会の元凶となった(私はそう思っている)のは、アベノミクスであり、それは企業の法人税を減税したこと、所得税の累進課税率を富裕層に有利な仕組みにしたこと、株等の金融所得に対する課税を分離課税(累進課税とは違い、利益額によって税金の割合が高くなることは無い⇒全て20.315%)としたこと、さらに政府によって株の利益を非課税とするNISAを「貯蓄より投資」などと国民に無責任に広げたこと、などなど。
その結果、大企業の減税は23年度で11.1兆円にもなり、内部留保額は23年度で600兆9,857億円となりました。消費税を5%に減税すれば約15兆円です。消費税は2014年から5%が8%に、2019年に8%から10%に引き上げられましたが、法人税は平成時代に7回も減税され、2014年34.62%だったのが今は23.2%となっています。
よく言われる、消費税の増税分は法人税の減税分の穴埋めとなってしまっていると言われる所以です。
そして、所得税の累進課税は4,000万円以上は一律45%となりますが、1億円を超える場合、大きくは金融所得が考えられますが、金融課税は先ほどのように20.315%ですから逆に負担率が減っていく「1億円の壁」という、富裕層優遇となっています。
相変わらず、我が国は大企業と一部の富裕層がより富を得、多くの国民は物価高騰にあくせくし、少ない貯金をNISAに投資しましたが、トランプ関税で株価は大きく下落し、利益だけでは無く投資分も泡となってしまいました。
このような状況に置かれている国民の鬱積は、直近の国政選挙に大きく影響することでしょう。