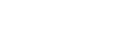宿泊税と総務省(ブログ3774)
- 2024年12月14日
道の宿泊税について、強引な議会運営と議会軽視について苦言を呈しましたが、結局、倶知安町の条件を飲んで、「同町が道税分に相当する額を道に納付する」ということで合意しました。しかし、その後、既に道と足並みを揃え導入を決定した20の自治体以外で、導入を検討している自治体から、「定率制」の導入に興味を持つ所が出始めました。
「定率制」の場合、宿泊費が値上がりすれば必然的に宿泊税も増収になりますが、「定額制」の場合は、一定期間の後に必要に応じて値上げの条例改正をしなければなりません。
また、海外の観光客の場合、「定率制」がスタンダードで理解しやすいこともあります。
総務省で問題が無いと判断すれば、今後の導入自治体は「定率制」の方に傾くことが想定されます。
そうなれば、「定額制」に固執していた北海道はメンツを失ってしまいます。
さて、そこで考えたのが、倶知安町との協議で「総務省が認めなければ、当初の道の考え方で進める。」という確約です。
道は、既に総務省と内々に打ち合わせが出来ていた可能性も否定できません。
つまり、倶知安町との間では1税2制度を認めながら、その裏では総務省が「2制度は認められない。」という判断を下すことに期待をかけているかもしれません。
そうなれば、道は全く悪者にならず、政府の判断であると言う「錦の御旗」の下で、倶知安町に定額制での宿泊税の徴収を求める事ができ、今後も宿泊税を導入するであろう自治体も道と足並みを揃える事も期待できます。
条例の中身とは全くそぐわず、自治体における特定目的税の趣旨(徴収自治体管内の観光振興)や納税義務者(宿泊者に課す税では無く自治体に課すことも出来る)、特別徴収義務者(宿泊を営むものだけでは無く自治体を指定する故知も出来る)の規定さえも飛び越えてしまう条例修正ですが、さてさて、今回の強引な宿泊税条例の可決成立後、27年4月の施行までの間に一体何が起き、条例の内容に齟齬が生じないのか、じっくり監視していきたいと思います。