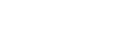政治とSNS(ブログ3823)
- 2025年02月02日
31日の道新に、成蹊大学野口雅弘教授の「SNS時代の民主主義」というコラムが掲載されていました。
野口教授はこの中で、ドイツの思想家ワルター・ベンヤミンが1930年代に書いた論文を引用してSNS時代の政治について寄稿していました。少し永くなりますが一部再掲します。
<ベンヤミンは、『民主主義、とりわけ議会は、目の前の対抗する立場の政治家達を説得するために、言葉が発せられる場所である。』と論じていましたが、さて今日では、議論の中身はもはや重視されない。ほんの一部だけが切り取られ、そこだけ何度も視聴される。
こうして派手な身振り、そしてわかりやすいスローガンが決定的なまでの意味を獲得する。
今日のこうした趨勢のすさまじさは、ベンヤミンの時代とは比べものにならない。
SNSで注目される政治家のタイプは、議会で力を発揮する政治家とは当然のことながら異なる。長期的な視点よりも即応性が、複数の観点を織り込んだ丁寧な議論よりもシングルイシュー(単一の争点)が、地味で粘り強い交渉より歯切れの良さが評価されやすい。
世界の多くの国で語られている「分断」もこうしたメディア環境による政治の変容と無関係では無い。
楽観的な展望を語ることはできそうも無いが、ここではあえて見栄えのしない、二つのことを述べておきたい。一つは、長期的な視野と総合性そして責任の観点を備えた政治思想(よい意味でのイデオロギー)が、これまで以上に重要になっているということである。
そしてもう一つは、政治家や一般の市民が政治思想を語り、それを相互に検討するのに必要な媒体として、既成メディア、とりわけ新聞に期待される役割が大きくなっているということである。時代の流れはあまりに激しいが、それに抗するたけに私たちが頼る事ができる資産が無いわけでは無い。>と主張していました。
私も、新聞を3紙購読していますし、仲間が配信している全国の新聞からピックアップしたニュースを毎日読んでいます。
新聞は、記者が様々な案件を取材して問題点を深掘りし、確実な裏取りを行い、反対の意見も掲載して記事にします。最近は「記名記事」も増え、誰が書いた記事かも明らかにしています。
今回、このブログに再掲した野口教授のコラムも、東京都知事選、兵庫県知事選、米国大統領選など、とりわけ、誹謗中傷とフェイクな拡散が選挙結果さえ左右し、ひいては政府や地方政治の政策にも負の影響を与えてしまうSNSの間違った使い方と、それを鵜呑みにして無責任に拡散してしまう危うさに警鐘を鳴らしたかったからだと思います。
そして、兵庫県知事とN党の党首の行動によって死を選ばざるを得なかった犠牲者が三人も出てしまいましたが、当の本人達は「我知らず」で逃げまくっています。
今年行われるであろう国政選挙や都議会議員選挙では、手ぐすねを引いている輩がメディアに顔を出しています。フジテレビでは無いですが、各テレビ局、そしてプラットフォームはその影響力を自覚し、視聴率や既読数にばかり血眼にならず、正確な内容を重視し責任の伴った配信をして欲しいと願います。