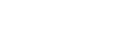能登半島地震視察1(ブログ3875)
- 2025年03月31日
視察が続き、5日間ほどブログをお休みしていました。何せ、アナログ人間なので、パソコンを抱えながらというのは苦手でして。
そんな事でしたが、今日からまた、いつものようにチョイと長めのブログを掲載します。
今回は、能登半島地震から1年2ヶ月後の被災地の状況を現地の議員の方からが案内してもらい、当時のお話を伺うこと、そして予期せぬ大地震の復旧・復興の経験を石川県の担当者からのヒアリングを受けるのが目的の視察でした。
石川県はまだ復旧のただ中にあり、交通機関も限られ、初日は単純に移動日となってしまいました。
函館空港から羽田空港、そして羽田空港から小松空港へ、被害のあった輪島市周辺には宿泊施設が取れなかったことから、レンタカーで約1時間半かけて金沢市へ。
機材繰りのために航空機が遅れた事もあり、チェックインは午後4時近くとなってしまいました。
翌日は、朝8時にホテルを出発し、約2時間で穴水町着、ここで、志賀町議会議員の堂下氏と合流して、被害が激しかった珠洲市に向かいましたが、目的地に行くまでの高速道路「のと・ふる里海道」は、道路がうねり波を打っていたり土砂崩れによる迂回やひび割れ、復旧工事があちこちで行われていました。
のとふる里海道から降りて県道に。山道から海岸線に向かう間も山肌が根こそぎ崩れさっている姿もあちこちで散見。さらに崩壊した家、おしつぶされて泥が流れ込んだままの家屋もあちこちに、1月の大地震の後、9月には線状降水帯が襲い、1日400mmの雨による河川の氾濫も重なり、田んぼは泥に埋まってしまっていました。
海岸線は更に酷く、国道249号線はほぼ全て土砂崩れの下になり、トンネルも土砂に埋もれてしまいましたが、とにかく、物資の輸送が重要な事から仮の国道として、元々は海の底だったはずの隆起した階段線を応急的に国道を建設して珠洲市までのラインを確保していました。以前の国道は、復旧など今後も出来ないだろうと思うほどの惨状でした。
途中からUターンして輪島市に向かいましたが、途中にあった 能登の名勝「白米千枚田」も畦が崩れて泥が入り、無惨な姿となっていました。
輪島市に入りましたが、朝市は火事による消失で建物は全て撤去され、焼け焦げたままの街路樹がぽつんと1本。
穴水町の海岸は、陸地が5m以上も隆起し漁港も今は海の中では無く砂の上に痕跡を残しています。海岸線は100m以上も陸地から離れてしまい、なんとも言えない風景が目の前に広がっていました。
曹洞宗の大本山総持寺祖院も被害を受け、歴史のある建物ですがあちこちで修復が必要な姿となっていました。
次の目的の志賀原発に向かいましたが、刑務所の塀のように周囲が囲まれて、建物の上の部分が見えるだけ、時間も無かったことから、今回は原発内を視察することが出来ませんでしたが、志賀原発は休炉中と言うこともあり、また、地震による施設異常も見つかったことからアプローチしても断られるだけだと想定しました。
明日のブログは、県庁でのヒアリングについて掲載したいと思います。