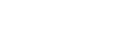食品ロス(ブログ3811)
- 2025年01月21日
コロナ禍が開けて、昨年は春から、少しづつ宴会が息を吹き返しました。
そして、昨年末は、インバウンドの数が増えたせいもあるのか、市内の居酒屋は予約も一杯という賑わいを見せ、年が明けた今は新年会など完全にコロナ禍前に戻ったような気がします。
そして、改めて目につくのが「食品ロス」です。宴会が最後の乾杯となってもテーブルの上には料理が半分近く残っており、誰も気にすること無くその場を後にしますが、残った飲食物は当然のごとく廃棄処分。
一部、養豚の餌として、また、肥料として再利用される場合も有りますが、それはほんの一部。昨日の新聞でも、食品製造業で約117万トン、外食産業で約60万トン、家庭系では約236万トンの食品が廃棄されていると報道されました。
一方で、子どもの7人に1人が貧困となっており、全国には1万ヶ所以上の「子ども食堂」が存在しています。そして、そこでは、発注した結果、売れ残った食品や企業などからの寄贈で食品等が集められますが、必ずしも十分とは言えません。そして、その子ども食堂には高齢者や、所得の低い若い方も訪れます。
これが、今の社会の矛盾ということなのでしょうか。
日本は、食糧の多くを海外からの輸入に頼っており、食糧需給率は現在約38%で、年々減少しています。実に62%が輸入の食品ですが、これが円安で単価が上がる一方となり、この2年間余りで原材料は約2倍、それは当然製品にも跳ね返りますから、毎月のように様々な食品が高騰していますし、異常気象のせいで生鮮食料品も大きく値段が上昇しています。
そんな事を知ってか知らずか、廃棄される食品は一向に減少していません。
私たちも、道議会の中で議員提案として「食品ロス削減を目指す条例(仮称)」を3月までにまとめ、4月から施行できるように準備を重ねています。
ただ、これは理念条例の域を出ない条例ですから、食品ロスを防ぐのは、個々の意識の問題となりますが、そこに行政としての取組が加われば、より皆さんに協力していただける機会も増えるだろうと思います。
常に「もったいない」を頭の隅に置き、食と向かい合いたいものです。